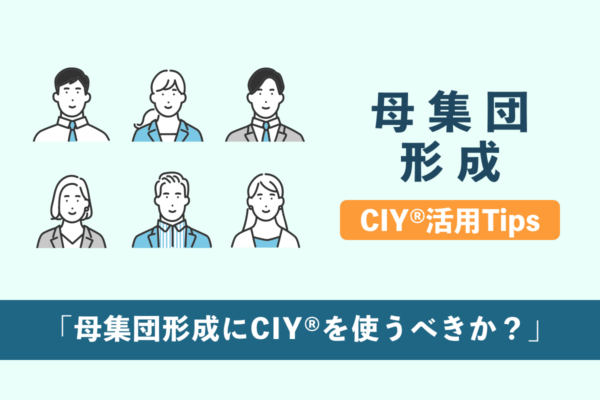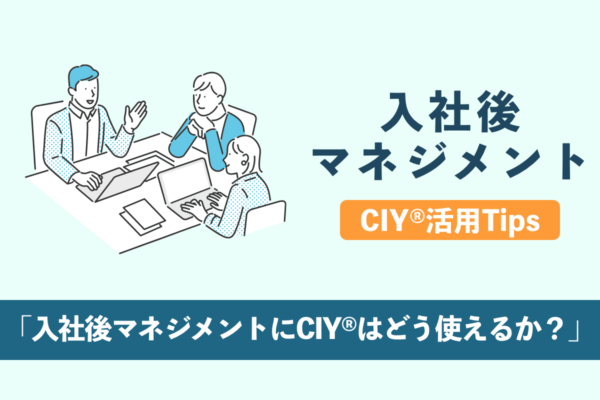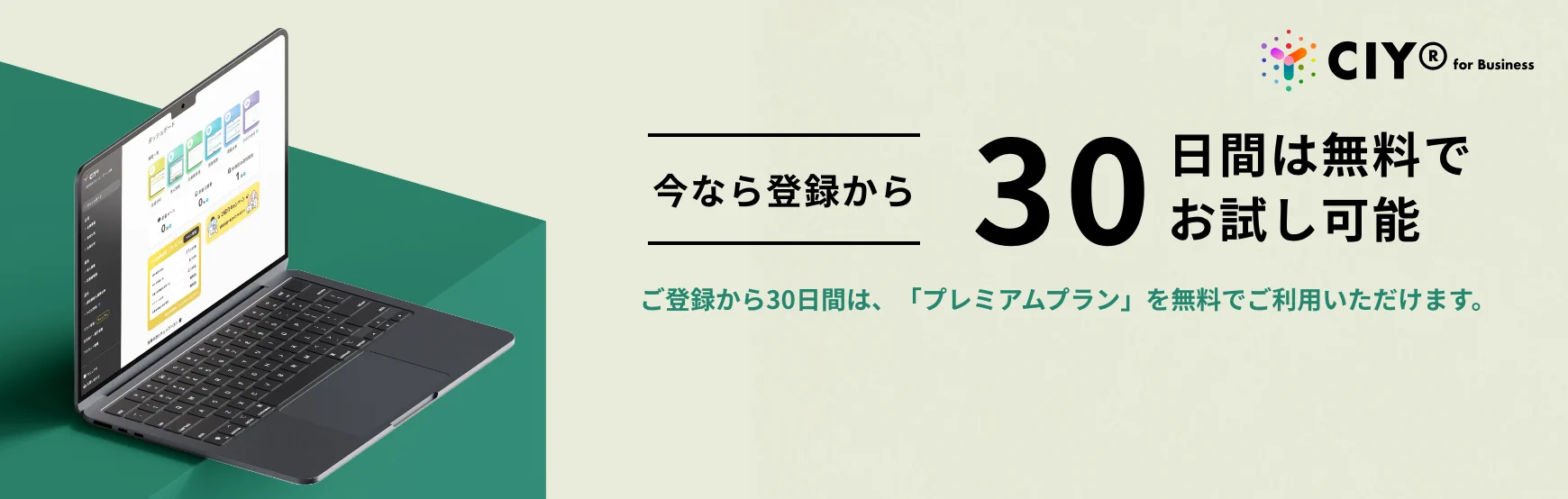更新:2022.09.19|公開:2021.12.02
採用基準作成にCIY®を使うべきか?

採用基準を作るメリットはかなり大きく、作らずに採用を進めることは困難といっても過言ではありません。
CIY®を使えばノウハウがなくても手間がかからず採用基準が作れて、活用による恩恵も大きいので、ぜひ使うべきと言えます。
採用の流れ
採用基準を作る → 母集団形成 → 書類選考 → 面接 → 入社後のマネジメント
このページでは、「採用基準を作る」について解説します。
他の項目については、各ページをご参照ください。
この記事の内容をホワイトペーパー(PDF)でもご覧いただけます。
無料ホワイトペーパーのダウンロードはこちらから >
目次
■そもそも採用基準を作るべきか?
◇採用基準とは?
採用基準とは、「どんな人材を採用するべきかのゴール」のことです。
ゴールがないとシュートが打てないのと同じように、採用基準が決まっていないと、どんな人を集めて選考すれば良いのかわからなくなってしまいます。
採用活動を始めるときには、採用基準を必ず作りましょう。
採用基準を分解すると「条件」と「特性」に分けられます。
採用基準 = 条件 × 特性
条件は、学歴、職歴、資格などの応募条件のことです。
求人票を作る際に必要になるので、ほとんどの企業では、「条件」は明確になっていると思います。
特性は、「自社に必要な特性」と「仕事に必要な特性」のことです。
この基準が明確であれば、候補者がその特性を備えているか、選考時の見極めポイントを押さえることができ、「質の高い選考」ができます。
◇採用基準を作るメリット
1. 選考をする際の、判断基準になる
応募者を全員採用する場合は別として、応募者の中から内定者を選考する場合には、合否の判断基準が必要です。
採用基準は、そのまま合否の判断基準になります。
2. 合否判断が人によってぶれない
採用基準を作って社内で明確にしておけば、面接官によって合否の判断基準が異なる、ということを避けられます。
3. 採用の振り返りができる
採用基準を作った上で内定者を出せば、後々「この内定は正解だったか?」「採用基準は正しかったのか?」など、当時の採用活動を振り返ることができます。
振り返って課題が見つかれば、改善していくことができます。
4. 求職者の惹きつけにつながる
基準を示すと、ターゲットとなる求職者を絞ってしまい、応募が来なくなるという不安が聞かれるが、実際は逆です。
基準がないと、誰にも響かないので応募が来にくいのです。
基準を示せば、それに適性が高い求職者が「自分のこと」と思えるため、応募につながりやすくなります。
◇採用基準を作らないデメリット
メリットの逆が考えられます。
- 合否を出す判断基準がわからない
- 面接を担当する人によって、合否判断がブレる
- 採用活動を振り返ったり、改善することができない
- 求職者の誰にも響かない
といったことが生じるため、採用基準を作らずに採用を進めることは困難といっても過言ではありません。
また、採用基準 = 条件 × 特性で考えると、以下のようになります。
【現状、これはできている企業が多い】
条件✕ 特性✕ →入社に至らない
条件✕ 特性◯ →入社に至らない
「条件」は明確にしやすいし、求人票に記載する&選考で確認するため、これは多くの企業でできているようです。
【現状、こうなってしまっている企業が多い】
条件◯ 特性✕ →入社するが早期離職
「特性」は明確にしにくいので、このケースがかなり多く発生しているようです。
【こうなればOKだが、たまたまかも?】
条件◯ 特性◯ →入社して、定着・活躍が期待できる
これが理想ですが、たまたまこうなった、ではなく意図的にこの状況を作りたいですね。
条件と特性の両方を明確にすることが、ファーストステップです。
「そもそも採用基準を作るべきか?」
採用基準を作るメリットはかなり大きく、作らずに採用を進めることは困難といっても過言ではないため、採用基準は絶対に作るべきと言えます。
■CIY®を採用基準作成に利用すべきか?
◇採用基準を作る方法
改めて、採用基準とは下記に分解できます。
採用基準 = 条件 × 特性
条件については求人票を作成する際に明確になる企業が多いので問題ないと思われます。
ここからは、明確化が難しい「特性」についてです。
CIY®を使えば、ノウハウがなくても「企業」と「仕事」の特性を手軽に明確にできます。
・企業の特性
企業ごとに企業風土、カルチャー、組織構造、制度、その他、色々な要素が異なります。
業種によって特性が方向づけられる部分もあります。
例えば、
- 医療は正確性や慎重性が重視される
- エンターテインメント業界では創造性や芸術性が重視される
ただし、同じ業界でも企業によって特性はかなり異なります。
- 同じ医療でも、総合病院と専門病院でも異なる
- 専門病院でも整形外科と小児科では異なる
さらに、同じ小児科でも、院長の方針や人柄、理念などによって、病院ごとに特色が異なるでしょう。
同じ業種でも、企業ごとに特色が異なるからこそ、同じ商品やサービスを購入するにしても、異なる選択肢が生まれるのです。
(それが消費者に多様な選択肢を与えており、企業同士の差別化にもなっています。)
自社の特色、特性を明確にできれば、「自社で活躍しやすい人材と、合わずに早期離職してしまう人材」を見極めるための基準ができます。
・仕事の特性
仕事によって、活動内容、必要な能力、進め方などが、かなり異なります。
例えば、1つの企業内でも、営業と経理とエンジニアでは、必要な特性が全く異なります。
営業でも、法人営業と個人営業、飛び込み営業と反響営業でも特性が異なるでしょう。
さらに、同じ法人営業でも未経験の若手社員と、営業チームを率いるマネージャーでは、必要な特性が異なります。
これら、仕事に必要な特性を明確にすることで、「候補者がその特性を備えているかどうか」を判断できます。
◇CIY®で特性を明確にする方法
採用基準 = 条件 × 特性
「特性」をさらに分解すると
特性 = 企業の特性 × 仕事の特性
となります。
企業の特性と仕事の特性を、それぞれ明確にするには高度なスキルを要するため、難易度は高いです。
大企業では、これまでのデータやノウハウを使って、採用基準を明確にして、採用成功できている企業もあります。
中小企業では、「特性」を明確にできず「条件」のみで採用している企業が多いため、早期離職→慢性的な人手不足に陥っている企業が多いようです。
CIY®では、
- 企業の特性を明確にする質問72問
- 仕事の特性を明確にする質問56問
に答えるだけで、知識がなくても手軽に「特性」を明確にすることができます。
結果として表示される「特性=求める人物像」のサンプルはこちら >
ここで明確になった「特性=求める人物像」を活用することで、
採用基準 = 条件 × 特性
を手軽に作ることができます。
◇CIY®を使わない場合どうする?
CIY®を使わなくても、「特性」を明確にすることはできます。
・企業の特性
企業の特性を構成する要素(業界特性、企業文化、組織構造、制度、チームなど)を明確にした上で、それぞれについて自社の特性を分析することで、企業特性が明確になります。
・仕事の特性
仕事の特性を構成する要素(仕事内容、必要な能力、求められるスキル、仕事の進め方など)を明確にした上で、求人を行う職種、それぞれについて特性を分析することで、職務特性が明確になります。
この場合は、構成要素を洗い出し分析するノウハウと、膨大な手間がかかることが予測されます。
「採用基準を作る際にCIY®を使うべきか?」
CIY®使うメリットはかなり大きく、使わない場合はそれなりのノウハウと膨大な手間がかかってしまうため、採用基準の作成にはCIY®をご活用ください。
■作成した採用基準はどのように活用できるか?
◇候補者の惹きつけ
「求める人物像(必要な特性)」を公開することで、求職者は応募をする前に「どんな人材が求められているか」を確認することができます。
企業の求める人物像に適性が高い求職者は「この企業は自分の価値観に合っているので、この企業で働いてみたい」と思えます。
※マイナビの2022年卒大学生アンケートでは、志望企業を選んだ理由の1位が「自分の価値観に合いそう」(44.9%)。
特性を明確にしてそれを開示することで、それに適性の高い候補者を惹きつけることができ、応募の質と量が向上することが期待できます。
◇選考基準になる
条件と特性が明確になれば、応募者の合否を決める判断基準になります。
- 合否を出す判断基準が明確になる
- 面接を担当する人の間で、合否判断が統一できる
- 採用活動を振り返ったり、改善することができる
といった活用が可能です。
「作成した採用基準はどのように活用できるか?」
CIY®を使った採用基準によって応募者の質と量を向上させ、社内で統一した合否判断によってブレのない選考が可能になるため、非常に活用できます。
採用の流れ
採用基準を作る → 母集団形成 → 書類選考 → 面接 → 入社後のマネジメント
他の項目については、各ページをご参照ください。