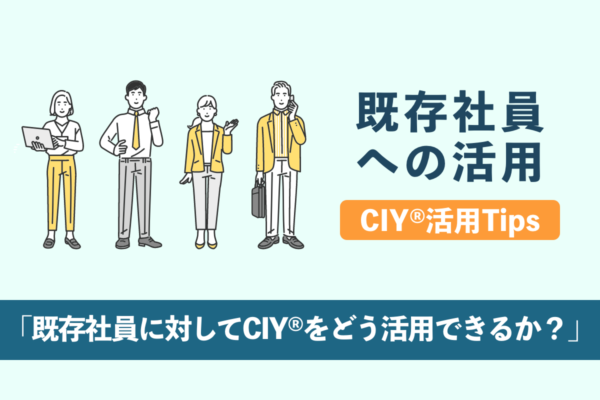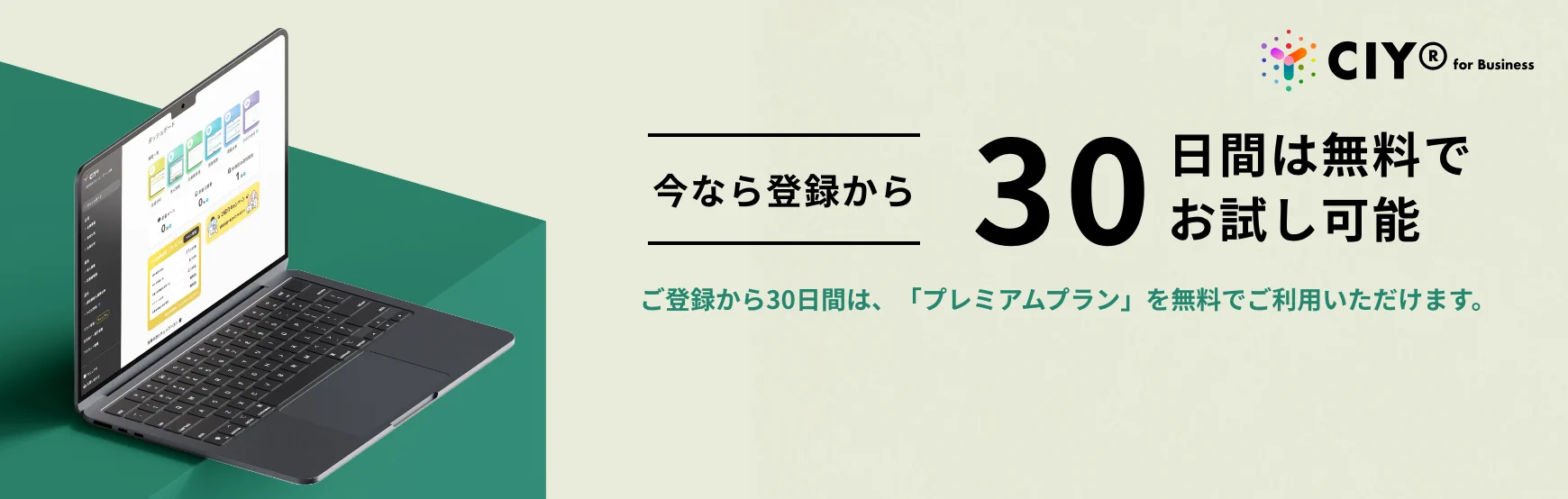更新:2023.09.12|公開:2021.12.02
面接でCIY®を使うべきか?

面接では必要な経験・スキルを有しているか、自社が求める必要特性を候補者が有しているか(適性があるか)、その他に大きな懸念点がないか、の3点を確認する必要があります。
CIY®の適性検査を活用することで、適性が高い点、低い点が客観的かつ手軽にわかり、ミスマッチが懸念される点を深堀りする質問例も提案されるため、特に中小企業では積極的に活用するべきと言えます。
採用の流れ
採用基準を作る → 母集団形成 → 書類選考 → 面接 → 入社後のマネジメント
このページでは、「面接」について解説します。
他の項目については、各ページをご参照ください。
この記事の内容をホワイトペーパー(PDF)でもご覧いただけます。
無料ホワイトペーパーのダウンロードはこちらから >
目次
■面接ですべきこととは?
◇条件に合致しているか確認、深堀り
採用基準 = 条件 × 特性
に沿って、「条件」と「特性」のいずれにも合致しているかどうかを、選考で見極めていきます。
学歴、職歴、資格など「条件」については、書類選考で見極めができます。
即戦力採用など、経験が重視される場合は、面接で経験の質や量を深堀りして確かめます。
(必要であれば、スキル測定のための試験・テストなどを実施しましょう。)
◇特性への適性があるか確認
書類選考だけでは見極めが難しいのが「特性」です。面接で自社への適性を確認していきます。
採用基準についてのページで解説している通り、そもそも自社の「求める人物像」が明確になっていなければ、自社に適性のある候補者なのか、比較して判断することはできません。
よくある適性検査では、候補者に適性検査を受けてもらい、候補者の性格や資質を確認しようとしますが、これは「候補者の特性(資質、性格など)」が明らかになるだけで、「自社への適性」はわかりません。
CIY®の求める人物像分析で、あらかじめ「求める人物像」を分析することで、
「自社が求める特性・能力」と「候補者の特性・能力」
を比較して、適性の高さを判断することができます。
◇条件・特性以外に懸念点がないか確認、深堀り
条件と特性の他に大きな懸念点がないかを、確認します。
例えば、
- 過去の会社でのトラブル
- 転職回数の多さ
- 面接中のコミュニケーションでの問題その他、選考のやり取りの中で気になった点
など、「条件と特性が両方問題ないとしても、採用しない理由がないか」を見極めましょう。
「面接で何を行うべきか?」
・条件面は主に必要な経験・スキルを有しているか
・特性面は、自社が求める必要特性を候補者が有しているか(適性があるか)
・その他に大きな懸念点がないか
この3点を確認することで、入社後に定着と活躍が期待できる人材か否かを見極めることが必要です。
■面接にCIY®を活用すべきか?
CIY®を活用することで、候補者が「自社に必要な特性・能力」を持っているか(適性があるか)を、客観的かつ手軽に見極めることができます。
◇マッチする点
まず、企業が必要とする特性に対して、候補者の適性が高い要因がわかります。
(下記、検査結果の「マッチする点」)

全23項目の中で、どこがマッチしているか、数字とグラフで把握することができます。
また、マッチしている項目についての解説も表示されます。
◇ミスマッチが懸念される点
企業が必要とする特性に対して、候補者の適性が低い要因がわかります。
(下記、検査結果の「ミスマッチが懸念される点」)

全23項目の中で、どの適性が低いか、数字とグラフで把握することができます。
また、ミスマッチが懸念される項目についての解説も表示されます。
◇面接で確かめるべきポイント
「ミスマッチが懸念される点」について、入社に際して問題ないレベルなのか、問題があるレベルでミスマッチしていいるのかは、適性検査だけではわかりません。
これについて、面接で質問して深堀りするための質問例が自動的に表示されます。
この質問例を参考にして、適性が低いと分析された項目について深堀りし、内定を出しても良いか判断しましょう。

また、書類選考から面接の段階で、気になったことや入社後に配属される現場のマネージャー・上長などに共有したいことは、候補者ごとの「メモ欄」に残しておくことができます。
- 面接で気になったこと
- 試用期間で検証したい点
- 配属後にマネジメントで気をつけてもらいたい点
などを、選考時に書き残しておくことで、入社後の振り返りや申し送りにご活用ください。
◇適性検査を行わず、構造化面接を活用する
適性検査は実施せず、構造化面接で合否を判断する方法もあります。
(構造化面接とは?)
構造化面接は、過去データの蓄積があり、そこから自社の分析がしっかりできている場合に成り立ちます。
Googleは自社の採用で構造化面接を取り入れていることで有名だが、Googleほどのデータ蓄積&分析能力があれば、構造化面接はかなり適していると考えられます。
データの蓄積がしづらく、面接機会の少ない中小企業では、構造化面接の導入は難易度が高すぎるかもしれません。
(過去データの分析が難しく、構造化面接実施の機会が少なくノウハウを得にくいため)
中小企業では、面接官がしっかり候補者を理解して
- 適性があるか
- 適性がない部分を理解した上で採用して問題ないか
を、個別に確認する方が現実的と言えるでしょう。
上記を確認するために、CIY®適性検査の実施を活用することができます。
(もちろん、構造化面接に挑戦しつつ、CIY®の適性検査も併用いただくのも◎。)
「面接にCIY®を活用すべきか?」
CIY®の適性検査を活用することで、適性が高い点、低い点が客観的かつ手軽にわかり、ミスマッチが懸念される点を深堀りする質問例も提案されます。
構造化面接の実施が難しい中小企業では、特に積極的にCIY®を面接に活用するべきと言えます。
採用の流れ
採用基準を作る → 母集団形成 → 書類選考 → 面接 → 入社後のマネジメント
他の項目については、各ページをご参照ください。